浜江 順子
私の第五詩集『飛行する沈黙』(第四十二回小熊秀雄賞受賞)のタイトルについて考えてみたいと思う。中世と現代を沈黙に引きずられるかたちで、空を飛ぶ。沈黙をエネルギーに飛行する。
そもそも沈黙は重いのか、軽いのか?重くても、沈黙ってヤツは飛ぶ時は跳ぶのである。重いからこそ飛ぶという考え方もある。重くて耐え切れなくなった時、沈黙は突如、アナーキーに飛ぶのである。それは詩として新たなエネルギーを携えて、縦横無尽に飛行する。言葉はそれゆえ、沈黙を飛ばした後はまた新たな沈黙を溜めることができる。「溜める」「飛ぶ」「溜める」「飛ぶ」、つまり、沈黙は「溜める」「飛ぶ」の円環作用を繰り返すことにより、我々の沈黙は磨かれ、おのおの自分の沈黙を通して詩を我が物にすることができるのである。自己にシコシコ溜めた沈黙から自己の創造も生まれるのであり、沈黙ほど大切なものはないといえるだろう。
各人の沈黙はそれぞれの沈黙を「沈黙嚢」(ちんもくぶくろ)に有すのであって、代用はできない。それぞれの沈黙には型があり、個性豊かでもある。まさに、恐るべき沈黙の力なのである。
沈黙についてはウィトゲンシュタインの哲学を通じて論考する崎川 修はこう語っている。
“対話を生み出すために必要なのは「沈黙」であるように思われる。もちろんそれは「おわり」としての沈黙ではない。むしろそれは「すでに語りうるもの」としての自己の語りをいったん埋葬し、その場所を「未だ語りえないもの」すなわち、他者の語りための「時間」として空けておく。そのための沈黙なのである。
このとき、言語的ニヒリズムはひとつの「方法」へと彫琢される。それは沈黙を媒介した、言語的現実の「死と再生」の経験を開く。そしてこのことによって、世界はまさに「時間」をその豊饒さとして受け取れることになるだろう。すなわち、死を挟んで対峙する過去と未来という「奥行き」と、そこを往来する無数の他者の戯れと言葉が、日常の言語ゲームの細部に密やかに浸透し、生命を吹き込むように思われるのである”(『他者と沈黙』―ウィトゲンシュタインからケアの哲学へー崎川修著2020年、晃洋書房発行)私が語ってきたことは、恐れ多いことだがまさにこのことのように思われる。
『他者と沈黙--ウィトゲンシュタインからケアの哲学へ--』崎川 修 より
もちろん、「沈黙」にこれほどの意味があると知ってこの詩集『飛行する沈黙』を書いたわけではなく、あとから「沈黙」の意味を知ることになる。まさに偶然の産物といえよう。
『飛行する沈黙』が沈黙を媒体として豊饒さを読者が受け取れたどうかはわからないが、
少なくとも「沈黙」はその詩のなかで言葉を通して自在に「沈黙」の重さと軽さを語り、自由に羽ばたいているように思える。
“(前略}中世の労働者たちのように水を求めて、身体の水をわさわさと共鳴させる。水は沈黙の奥に、清水のようにある。ペストを恐れぬ男たちは、ペニスを揺らし、修道院でふて寝して、脳には蚊が飛んでいる。(中略)
セイヨウアサガオを噛んで「いま」に迷い出た私は行方不明の自分を探している。ヨーグルトの詰まった腸を揺らし、祖父の前掛となる。見えないものが見えないままに、沈黙自体となるほかはない。”(『飛行する沈黙』2008年、思潮社発行)
『飛行する沈黙』では沈黙は現代と中世との間を飛行するのみでなく、もちろん、行方不明の私を、言葉を、沈黙とともに探している。沈黙はいわば、私の大切な宝としてひしと胸に抱えられている。そして、この『飛行する沈黙』は、「白昼の爪」、「少女の歌」、「飛行する沈黙」、「茅の目をした少年」、「抜かれ、」「泥の流れ」、「もろい肉」、「細菌のごとく」、「空の芯」、「化け方が、うにゅうにゅだ」、「冷血みぞれ」、「猛獣使い」、「酸素欠乏危険場所」、「皿いっぱいの指」、「二分の一の顔」、「膜と膜のはざまで」、「死声、垂れる」、「鬱なる陰嚢」、「犬色花心」、「雨越し、狂気霞」、「脳虫のゆらぎ」、「追突するあぶら蝉よ」、「盲目の木」、「薄氷からの実」、「森のかなたへ」の全二十五作からなり、奇しくもそれぞれが飛行する詩となっている。
M・メルロー=ポンティが『シーニュ』の中で、
“要するに、われわれは、発言される以前の言葉を、言葉をとり巻くことを止めずそれなしではことばが何ものも語ることのないあの沈黙の背景を考察しなければならぬ。あるいはまた、言葉に混じりあっているあの沈黙の糸をむき出しにしてみなければならぬ”
『シーニュ1』粟津 則雄 より
(『シーニュ1』(粟津則雄訳、みすず書房)
というように、沈黙は詩において極めて重要な要素であることは間違いない。
これからも私はすこしギザギザの私の沈黙を大切にしながら、詩をつくり続けていこうと思っている。時には自らの沈黙に溺死ししそうになりながら。
了





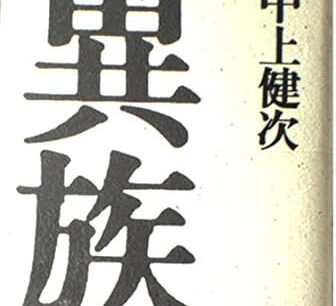


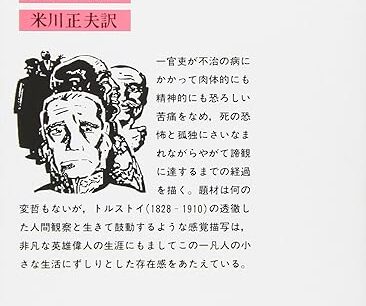

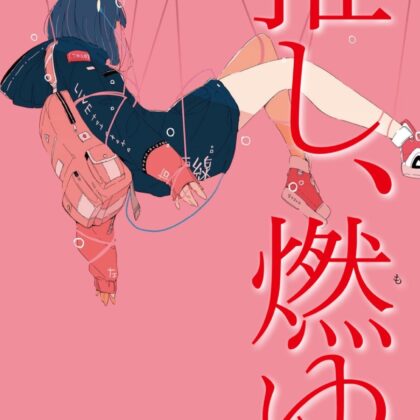


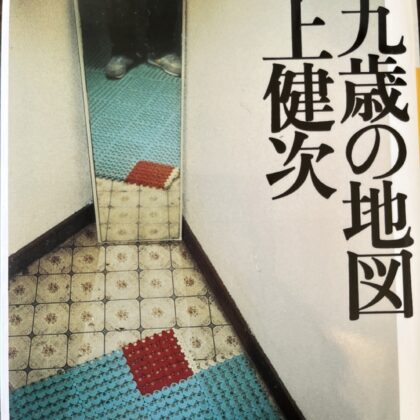


コメント