南野 一紀
イントロデュース
読者のみなさんのなかには、都会に住んでいてあくせく仕事をしながら、休日はシティライフを満喫している人もいるでしょうし、地方に住んでいて、仕事は忙しいけど、休日は自然に触れ合う機会がたくさんあるという人もいるかもしれません。世の中には、人の数だけと言ってしまうと大袈裟ですが、数多くのライフスタイルがあります。
読者のなかには、湘南の自然の多い場所で、ゆっくり生活したいと思ったことのある方もいるのではないでしょうか?
本作は湘南の稲村ヶ崎が舞台になっています。季節の移ろいを感じながら生きる、父子とご近所の兄妹のお話です。
本作の評論に入る前に、「保坂和志っていったいだれなの?」と疑問に思われた方のために、保坂和志氏自身についての説明をしたいと思います。
作家紹介
一九五六年生まれ。山梨生まれの、鎌倉育ち。早稲田大学卒業後、西武のカルチャーセンターに勤めます。一九九〇年、『プレーンソング』でデビュー。一九九三年、『草の上の朝食』で野間文芸新人賞を受賞。一九九五年、『この人の閾(いき)』で芥川賞を受賞。一九九七年、本作『季節の記憶』で谷崎潤一郎賞、平林たい子賞、受賞。
保坂氏や町田康氏を含め、一九九〇年前後に出てきた、セゾン系列に関係にある作家をセゾン系と括ることもあります。
村上春樹氏と同じくジャズが好きで、「フリージャズを好んでよく聴く」と話す保坂氏。ジャズ以外にも、映画や将棋や哲学が好きで、将棋や哲学についての本も書いています。
愛猫家としても知られていて、小説に猫がよく登場することでも有名です。画家の小沢さかえ氏と共著で『チャーちゃん』という猫が主人公の絵本も出版しています。
私は保坂氏の作品が好きで、『季節の記憶』も長編ですが、二回読みました。
著者紹介も済んだところで、『季節の記憶』のあらすじに入っていきたいと思います。
あらすじ
本作は先ほど述べた通り、湘南の稲村ヶ崎を舞台に、父子とご近所の兄妹が交流しながら、季節や時間の移ろいを感じつつ、生活するという作品です。
コンビニ本のライターをやっている主人公の「僕」と幼稚園に行かずに、親や周囲の人々から自宅で教育を受けている息子の「クイちゃん」とご近所の便利屋をやっている「松井さん」とその手伝いをしている「美紗ちゃん」の四人がベースになり、その四人に関わる人々である、ちょっと神経質な感じの女性「ナッちゃん」や、その娘の「つぼみちゃん」や、ゲイで人懐っこい男性「二階堂」や、旅館に勤めつつ、新しい宗教を考えている男性「蛯乃木」が登場します。
本論
保坂氏の作品の特徴なのですが、一文一文が長く、やわらかい言葉遣いで、哲学的な思弁や会話を展開することが多いです。本作も哲学小説になっていて、自然に触れながら、哲学の話をします。このように書くと、「相当な文学通じゃないとわからない、すごく難解な小説なんじゃないか?」と思う人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
冒頭の部分を引用してみましょう。
僕が仕事をはじめるとさっき昼寝についたはずの息子がニンジャの格好で部屋に入ってきて、
「ねえ、パパ、時間って、どういうの?」
と言ったのだが、僕は書きかけの文の残りの数語を書ききるまで答えなかった。
「ねえ、パパ。ねえ、パパ。――ねえ、ねえ。パパ、パパ。
パパ、パパ、パパ、パパ
パパ、パパ、ねえ、ねえ」
と、猫の「ニャア、ニャア」、アヒルの「ガア、ガア」、羊の「メエ、メエ」と同じように「ねえ、パパ」「ねえ、パパ」を連発しはじめ、僕はサインペンを息子にわかるようにはっきりした動作で音をたてて、机に置いて、
「終わったよ」
と、息子を見た。
そのあと、時間というのは大きな木のようなもので、種が成長して、「クイちゃんもパパも美紗ちゃんもおばあちゃんも、みーんな入っちゃてて」と説明します。
途中でクイちゃんは、飽きてしまい美紗ちゃんのところへ遊びに行ってしまうのだけど、この作者の意図とは違う方向へ行ってしまうような思い通りに行かなさが保坂氏の小説のリアリテイで優れているところなのです。構造がないわけではないが、変に対比的、構築的に作品を書かないところが保坂氏の作品の特徴です。
保坂氏の作品は「リアリズム小説=暗い小説」という、昔から日本文学にある定義を改めたところが新しいと私は思っていて、事実、それまでのリアリズム小説というのは、暗く重たいものが多かったのです。保坂氏のリアリティは明るいものでした。それが読者に希望をもたらすことも、多かったと思いますし、現在でも保坂氏のファンは多いです。
本作のすべての部分に触れていると、かなり分量が増えてしまうので、後半の主人公の「僕」や「松井さん」が「季節の記憶」を感じる場面を論じていきたいと思います。
引用をすると長くなってしまうので、概要を説明したいと思います。
「秋の日は釣瓶落とし」の時期は、人は言葉でできていることを実感するということを松井さんは言います。松井さんの話によると、言語っていうのは渦状の力の流れで、渦になっている中心が人間だということなのだそうです。適応能力とか遺伝とか本能とか、他の動物がダイレクトに機能しているものが、人間は言語の流れにいったん還元される。そして、文字とは限らない、言語が心の隅から隅までを作っているのだけど、季節を感じる瞬間、たとえば、稲村ヶ崎の方へ一三四号線を車で走っていると、西の方は夕日の気配が残っていて、東の方は完全に夜になっているような、そんな瞬間に、人は言語からズレる。そのズレを味わうことが大切だと、松井さんは言うのです。
つまり、人間の内在しているエネルギーが言語的なものを引き寄せていて、適応能力を失いはじめてから、言語で説明できない自然やズレを感じ、人間は人間になっていくという話だと私は解釈します。
郷愁との邂逅を果たした「松井さん」は、一人の大人になったということなのでしょう。世界はエネルギーにより成り立っていて、時間がゆっくり流れ出すとき、人間は精神的に寛解することもある。人が人であるために必要としてきた言語という機能を手放すことなく、生きることは難しいです。原始共同体には人は戻ることはできないので。しかし、人間社会のなかで、自然にふれ、郷愁を知ることで、もともと他の動物と同じように動物的側面も強かった動物的なものを取り戻して、大人になっていく、ということも可能なはずです。
私はこの小説を読んで、自然に触れたり、身体を動かしたりすることの大切さを知りました。
人間は人間であるがゆえに、普通の動物にわかっていることが、わからなくなってしまうこともきっとあるのでしょう。私も湘南に住んで、自然と戯れながら生きてみたいな、などとこの小説を読むと思ってしまうのですが、なかなか現実の仕事があるので、そういうわけにもいかないですが、老後はそんな生活もいいなとか思ってみたりします。まぁ、まだ先の話ですが。
いろいろ長く語ってしまいましたけど、保坂氏の小説は、「郷愁への統一」や「自然との邂逅」がテーマになることが多いです。
養老孟司氏の解説含め、文庫本で三六七ページあるので、だいぶ長い本ですが、読後の達成感はひとしおでしょう。
解説、評論できなかった部分もたくさんあるので、保坂氏の『季節の記憶』をぜひ実際に読んでみていただけると幸いです。
読者のみなさんも、きっと湘南に行きたくなりますよ。
参考文献
・保坂和志 『季節の記憶』 初版 一九九九年 中央公論社





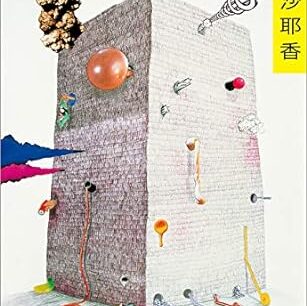




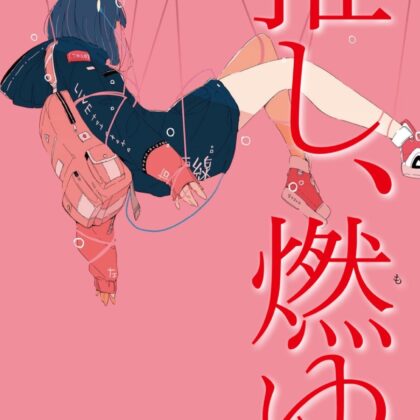





コメント