南野 一紀
イントロデュース
読者のみなさんは細く長く生きながらえて、なにもなく死ぬよりも、太く短く華々しく死にたいと思ったことはありますか? 主人公の三好の生はまさしくそういったものでした。あだ花のように咲いて散る彼には、罪があったけど、罪に気がつくだけの汚さがなかったのです。彼の乱暴でありながら、美しい生はきっと人を感動させることでしょう。
中上健次氏と言えば、コトノハ文学教室の講師であり、すばる文学賞の受賞作家でもある中上紀先生のお父さんにあたる人なわけですが、「中上健次っていったいどんな人なの?」と疑問にもたれた方のためにも、中上健次氏本人について語っていきたいと思います。
作者紹介
中上健次氏は和歌山県の新宮市出身の作家で、新宮高校卒業後、予備校を経て、羽田空港で肉体労働をしたのち、作家になった人物です。戦後生まれ最初の芥川賞作家としても有名で、『推し、燃ゆ』を書いたことで知られる、宇佐見りんも中上氏を尊敬しています。「中上健次以降の日本の作家の作品は文学じゃない」と言う人もいますし、「中上健次の死=日本近代文学の終焉」と言う人もいます。
予備校時代は、あまり勉強はしなかったようで、新宿にあったジャズ喫茶に入り浸って、悪い遊びをしながらジャズを聴きあさっていたのだとか。ジャズ喫茶ヴィレッジヴァンガードによく入り浸っては、友人と語り合ったという思い出は、ジャズ作品集『路上のジャズ』という本に克明に描かれています。その本のなかには、「鈴木翁二 ジャズビレ大卒」というエッセイもありますが、中上氏もまた「ジャズビレ大卒」だったのでしょう。結婚したのちに、芥川賞を受賞し、有名作家になり、アメリカや韓国やフランスなどに滞在し、作家活動を展開しました。
中上氏のことを、「気性の激しい性格の人だった」と言う人もいますし、「ジェントルでやさしい人だった」と言う人もいます。人によって、作品も人柄も賛否両論がわかれる作家なんでしょうね。
一九九二年に他界された中上氏ですが、毎年、夏に「熊野大学」という和歌山県で行われる中上健次氏に関するセミナーには、多くの人が来ていました。
その他、本人に関することで言えば、晩年は対人恐怖が募って、自室からあまり出ない生活を送っていたという説もあります。
そんな命を燃やすようにして、激動の人生を送った中上氏ですが、本作「六道の辻」はいったいどんな作品なのでしょう? 評論していこうと思います。
あらすじは、次のようなものです。
あらすじ
和歌山県の新宮に住む、三好という男性は泥棒をやったり、女性に売春をさせたり、料亭で働かせたりして、暮らしていました。一見すると、なにをして生計を立てているかわからない三好です。十九歳の三好は泥棒をやったときは、楽しかったけど、そのあとは退屈な人生だと思うようになります。ヒロポンという薬物を濫用もしているのですが、気は晴れないまま。中本の一族血が混ざっている三好は、仕事が好きではなく、女性と遊んで暮らす、一族の血を憎んでいました。そして、自分もその一族の人間だと気がついているのです。
三好はある日、盗みに入った家の亭主を包丁で刺して、殺し、亭主の血が噴き出るなか、女性とセックスをします。
そして、オリュウノオバという地元の産婆さんに助けられて、命かながら助かるのですが、その翌日勝手に家を出て、女性から金をせびり、飯場に向かって、仕事をします。しかし、ヒロポンの打ち過ぎか原因は不明ですが、目が見えなくなって、みんなしみったれて生きていると思い、さらにはこんな人生なら死んだ方がいいと考え、女性を売り飛ばした料亭の庭で首を吊って自殺します。
最後はオリュウノオバが三好の刺青の龍が、身体から抜け出して、空へ飛んでいくのを目にして終わります
あらすじとしては以上です。
本論
この作品は、「熊野大学二〇二二」で松浦寿輝氏が、最後のページのテクストを取り上げて、「フリージャズのような文体である」と評していましたが、まさに情動に任せた、フリージャズのような文体だと私も思います。『千年の愉楽』のなかでは、登場人物もそうですが、日本語が活き活きしていて、文学好きの私からすると思わず、笑うのを禁じ得ないような美しい文章です。
そんな文体で描かれている「六道の辻」ですが、内容にも触れてみましょう。
三好は泥棒はやるし、女性は売り飛ばすし、人は殺すし、仕事も続かないし、とにかくとんでもない人間です。倫理ということがわからない人間なのでしょう。しかし、世の中には一定数、そういう人間がいて、本作品はそんな救いようもない生を肯定する小説だと感じました。もちろん、犯罪はいけないですが。
三好は世が世なら、英雄伝になるような人物だったのかもしれません。しかし、平和すぎる時代の地方の町で育ってしまった三好には、羽ばたく可能性がなかったのです。そんな三好に最後、背中の刺青の龍が飛んでいく表現をすることで、時の翼を与えたのが、せめてもの救いだったのでしょう。綺麗すぎる生はときに社会悪にもなってしまうという残酷な運命を、三好は本能的に受け入れて死んだのです。
小説のなかには、三好が若い衆を集めて、ヒロポンを打ったあとに、オリュウノオバに呼び止められて、「泥棒で生きていけるほど、簡単な時代じゃない」という内容のことを言われるのですが、三好は「最近人生がつまんないから、龍の刺青を掘った」という内容のことを言い、龍の刺青をオリュウノオバに見せます。
私はこのシーンが大好きで、たとえ、運命が悲劇的だったとしても、小さな一個人に埋没する生だったとしても、華々しく生きてやろうじゃないかという三好の心意気が見えるような気がして、勇気づけられるのです。こんな勇気づけ方は中上健次氏にしかできません。
作家論になってしまいますが、中上健次氏は左翼だったし、日本の民族意識を大切にしていましたが、その実、両方ともを恨んでいたのではないかと思います。恨んでも恨み切れにないくらい。しかし、それらを逆手にとって、文学に昇華する才能は中上健次氏ならではだと感じます。中上健次氏が左翼や日本の民族意識を恨んでいたのは、初期短編を読めば、火を見るより明らかです。そもそも、「赤い儀式」のあとがきでは、「日本人である必要はない」と明確に述べていますし、その上で、左翼の人間がギリシア悲劇にこだわるのも変な話なので。もちろん、昔の左翼は西洋思想への憧れを強く持っている人は多くいました。しかし、中上健次氏の場合は、本質的に右翼だったのではないか、と感じます。小説からみなぎる、強さがその証拠です。私からすると、完全に右翼の人です。
中上文学が否応なく抱えることになった存在の悲劇性は、罪の意識と罪の意識のなさのあいだの揺らぎにこそ本質があると思います。罪の意識はすなわち、存在を縛り付ける反面、輝かせもするものです。罪の意識のなさは、エゴであり、ロマンを追い求める精神であり、それもまた存在を輝かせるものです。両方とも極めれば美しく輝くもので、中途半端だと汚いまま残るものであり、中上文学はその汚さのあとも垣間見えるのですが、それを必死に振り切ろうとする精神性が複雑さを生み、より美しく人の目に映るのでしょう。
三好は生まれ持って、世の中から厄介払いされるような存在だということに気がついて生きて、魂の大きさよりはるかに矮小に死にました。本来ならもっと疎外感を全面に出して、卑屈に生きてもいいところなのですが、三好の生き様はそうではなかった。あくまでも、綺麗に生きたのです。その美しさの本質は存在の悲劇性なのです。存在の悲劇性は罪の意識と罪の意識のなさのあいだの揺らぎにこそあります、というように、メビウスの輪のようにループする話なのですが、中上文学の問題意識の大きな部分を占める「血縁」と「罪」が強く逞しい中上健次氏の美学のもとに結晶したのが、本作『千年の愉楽』の「六道の辻」であると思います。
中上健次氏の「六道の辻」、ぜひ読んでみてください。
参考文献
参考文献
※中上健次 『千年の愉楽』 初版 一九九二年 河出文庫









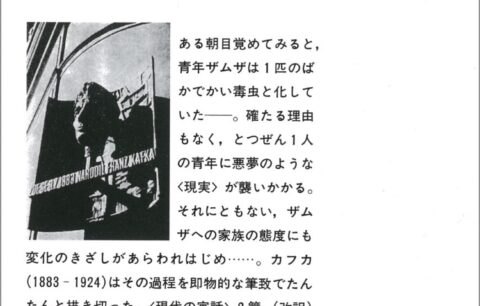
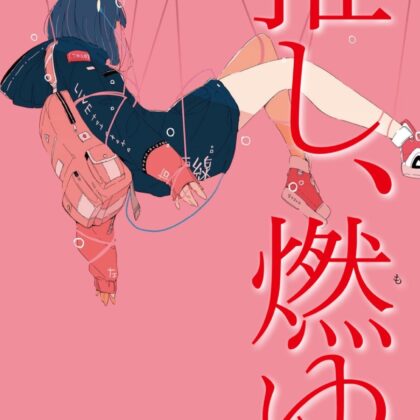


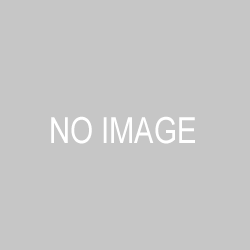

コメント