評論 フランツ・カフカ 『変身・断食芸人』所収「断食芸人」
南野 一紀
イントロデュース
読者のみなさんは断食することの辛さを感じたことはありますか? 断食芸人の苦痛や苦悩は想像を絶するものだったと思います。食べないというのはいったいどういうことなのでしょうか? それはすなわち、成熟を拒否することやエゴを弱くすることの表現なのだと私は思います。
本作の評論に入っていく前に、「フランツ・カフカっていったいどういう人なの?」と疑問に思われる方もいるかもしれないので、カフカ氏本人について述べていきたいと思います。
作者紹介
一八八三年生まれ。現在のチェコ出身。当時はオーストリア=ハンガリー二重帝国だった。ドイツ語作家。プラハの裕福なユダヤ人の家に生まれます。プラハ大学で法律を学んだのちに保健局に勤めながら、作品を執筆しました。一九二四年に咽頭結核により、この世を去ります。
代表作に『城』、『審判』、『変身』があります。
生前は『変身』数冊の著書がごく限られた範囲でしられるのみでしたが、遺稿が友人のマックス・ブロートにより発表されて。再評価される。現在では、マルセル・プルースト、ジェームズ・ジョイスと並んで、二〇世紀を代表する作家として見做されています。
影響を受けた作家に、ドストエフスキーやニーチェやゲーテをあげていて、影響を与えた作家に、サルトルやカミュやロブ=グリエやガルシア・マルケスやミラン・クンデラや安部公房や小島信夫がいます。
一説によると、統合失調症(当時の分裂症)であったとの説もあります。
父との仲が悪く、父親に大学で哲学専攻を希望したら、「失業者志望」と冷笑されるというエピソードも残っている。アフォリズム集にも、父親に対する名言として、「あの振る舞いはなかったんじゃないですかね」ということを綴った文章もある。
普段はおとなしく、礼儀正しい常識人として周囲に見做されていたとの話もある。
そんなカフカ氏ですが、本作の「断食芸人」はいったいどんな作品なのでしょう。
あらすじ
断食芸人は名の通り、断食を見せ物にしてお金を稼ぐ、芸人。四〇日間の断食をしては、興行師にパフォーマスをしてもらい、いかに断食芸人が断食に耐えたかを紹介してもらう、といった芸を見せる。断食芸人本人は、もっと断食できるのに四〇日で終わりにされることに、憤りを感じもしていた。見せ物をする際に、自分を抱きかかえてくれる婦人二人を、一見やさしそうに見えるが、その実は厳しい性格をしているというようにみなしている。断食芸人の断食芸は次第に飽きられて、断食芸人は興行師の元を離れ、サーカスの一団と契約する。最後は忘れられたように、藁のなかから発見され、豹に食われて終わる。
以上が、本作のあらすじになります。
本論
私は「断食芸人」を読むのが辛くて、辛くて仕方なかったです。カフカの苦しみや悲哀が伝わってきて、胸が詰まりそうな思いで、何回かにわけて読み終えました。
冒頭にも書きましたが、断食とは成熟を拒否することやエゴを弱くすることの表現であり、一種の自己否定でもあります。自己否定という言葉は本文中にも登場するので、断食の自己否定性はほとんど間違いなく、「断食」という言葉の意味に作中では介在していたでしょう。
本作品を読むと私は、スイス人のジャコメッティの細く縦長の彫刻を思い出します。あれらの作品は、実存的な不安を表現しているとよく言われますが、カフカ氏の作品もそのような実存的な不安が表現されていたのではないでしょうか。自分の精神がやせ細るまで、自己否定に追い込む断食芸人のストイックさは、ギリシア悲劇ともまた違った、ヒロイズムのほとんどない悲劇だと私は感じています。
ポストモダンという言葉には諸説ありますが、一説によるとオーストリアの精神分析学の祖、ジークムント・フロイトからはじまっているとも言われています。カフカ氏と同じ東欧の人ですね。精神分析によると、日本がうつ病圏であるのに対し、ヨーロッパは統合失調症圏であるという説があります。つまり、精神病理の質が異なるのです。
そんなポストモダンの先駆であったフロイトを生み出した、東欧という土地柄も、作品に色濃く反映されているのではないかと感じます。ポストモダンは近代を乗り越えようという、思想のことですが、特徴として、表面に浮かびたっている記号で言葉遊びをする、無意識の賛美、内面よりも外面を強調するといったものがあります。
しかし、カフカ氏の作品は東欧の作家の多くがそうであるように、本質論的な視点が鋭く、読み応えがあります。本質論的な視点には長けているのですが、超本質的な視点を思考するような強さが東欧の作家の多くには欠けていて、その辺は「断食芸人」の弱さであり、勇敢さに欠ける部分ではあるのですが、その部分がまさに美しいと賛美する人も多くいます。
特に日本では、自分を殺し、調和を重んじるこころが重視されていて、「和をもって尊しとなす」や「滅私奉公」という言葉もあるくらいで、そういった意味で、カフカ氏の「断食芸人」は日本では評価されるべき作品のはずなのですが、どちらかというと、『変身』の方が有名でよく読まれています。おそらく、物語の設定の妙が人のこころを惹くのかもしれません。とにかく、『変身』に比べると、「断食芸人」の認知度は低く、名作でありながら、世間ではほとんど相手にされていないのが現状です。
話は横道に逸れてしまいましたが、作品の最後に動物小屋と並んで断食芸人のおりが並置されて、動物の叫び声が断食芸人を苦しませるシーンがありますが、これも断食をして、エゴを弱くすると、動物のような精神性の人間とも苦しみを共にしなくてはいけないという精神的苦痛の表現だと思います。
イタリア語に「ピエタ」という言葉があります。強い者が弱い者の苦しみや感覚に共感することなく、苦しみに加わり、上から手を差し伸べるという言葉なのですが、「断食芸人」の場合は、「ピエタ」ではなく、「共に苦しむ」という姿勢をとって弱い者と接しました。作中には明記されていませんし、明記されていたらあまりに図々しくなってしまうので、書かれなくて正解だと思うのですが、「食べることやエゴを強くすることのできない人」の悲しみに寄り添う行為こそが断食芸人にとっての「断食」でもあったのではないでしょうか。それが不幸のはじまりでもあったのかもしれません。
イタリアの詩人ダンテ・アリギエーリの『神曲 地獄篇』にも、「大食の罪」により地獄に落ちている人がいます。やはり、断食を肯定しないまでも、神曲の世界においても大食は罪だったのです。
作品のラストに、豹の肉体が高貴さを呈しているといった描写がありますが、これも一種の自己否定的な皮肉で、まるで「同じ見せ物なら豹になりたかった」と言わんばかりの描写です。気高さもなく、勇敢さもなく、ただ痩せ衰えて、豹に食われて死んでいく断食芸人の一生に価値はあったのかと問われれば、エゴを強くすることに拒否感のある観衆をある意味で肯定したという点にあるのではないでしょうか。それが正義や善であるとは言えないかもしれませんが、確かに一部の人を勇気づけたのは確かです。
日本の小説家保坂和志氏もカフカ氏が大好きで、『カフカ式練習帳』というタイトルの作品まで書いているくらいです。保坂和志もまたカフカ氏の作品の魅力に共感する作家なのでしょう。
フランツ・カフカ作「断食芸人」、ぜひ読んでみてください。
参考文献
・フランツ・カフカ 『変身・断食芸人』 初版 二〇〇四年 岩波文庫
・ダンテ・アリギエーリ 『神曲 地獄篇』 初版 二〇一八年 河出書房新社








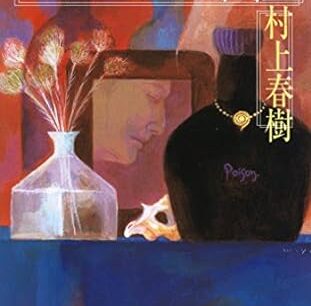

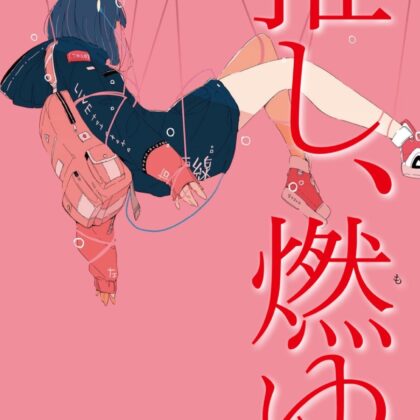


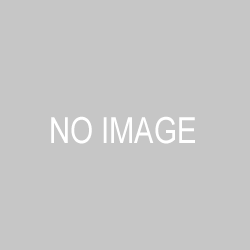


コメント