冨田 臥龍
イントロデュース
読者のみなさんの中には、この高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』を知っている人は、わりと多いと思います。最近の作品ですからね。
作者紹介
高瀬さんは愛媛県出身。立命館大学文学部、哲学専攻卒業、現在、東京在住。
2019年(令和元年)『犬のかたちをしているもの』で第43回すばる文学賞受賞。
2021年(令和3年)『水たまりで息をする』で第165回芥川賞候補。
2022年(令和4年)『おいしいごはんが食べられますように』で第167回芥川賞受賞。
あらすじ
高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』は、次のような作品。
若いサラリーマン男性の二谷は、芦川さんと付き合っています。
押尾さんも、二谷に気があります。
芦川さんは、仕事はできないが、色々な食べ物を料理して、職場に持ってくるようになりました。スイーツなども。職場はこれを歓迎するわけです。
押尾さんは、学生時代、チアガールなどをやっていましたが、好きだからやっていたわけではなかったのです。二谷も、本当は文学が好きだったのですが、実社会適応のことを考えて、経済学部を選びました。文学部を選んだ、その頃付き合っていた彼女に嫉妬しました。
本当に好きなことを選ばず、社会適応や、仕事だからきちんとやらないと気が済まない性格ゆえに、あまり好きではない仕事をやり続ける自分が嫌な者同士だったのです。
芦川さんは、仕事はできないですが、自分の好きなことをやって生きているタイプです。
芦川さんが職場にもってきたケーキなどが捨てられている事件が起こりました。
二谷も、ひそかに捨てていたわけです。押尾さんは、二谷が捨てていたと思っていましたが、他の人も捨てていたようです。事件発覚で、職場が動きます。
押尾さんは退職が決まりました。芦川さんは職場に戻り、二谷と結婚予定です。
二谷は人事異動で転属です。押尾さんは負け、芦川さんは勝ったわけです。
二谷は、勝ったのか、負けたのか・・・。わかりません。
本論
どう読むか? ですが、背景には、二つの考え方と、現代の新自由主義の思想が。
二つの考え方とは、まず、一つ目は、利他的に振る舞いながらも、自己の利己性を通し、自分の好きなことをやる、リベラルの考え方。
二つ目は、利己的に振る舞いながらも、自己の好きなことをやる押しの強さがなく、結果的に、社会の他者から必要とされることをこなすに至る、保守の考え方。
「おいしいものを食べたい」というのは、近代のエゴイズム。
ここに、科学と資本主義が重なるわけです。
「他者においしいものを食べさせたい」は、利他的に振る舞っているが、自分の利己性を内に秘めている。自分のやりたいことしか、結局やらない。やれない。リベラル主義。
「他者の善意を踏みにじりたい」は、利己的に見えるが、実は、一見利他的に振る舞って、その実、自分のやりたいことしかやらない、やれない、リベラルの考え方を否定しているわけです。自分を通すには押しが弱く、結局、社会が自分に割り当てた役割をこなす。だが、本当は、リベラルの偽善性を嫌っているのです。露悪主義。保守主義。
芦川さんはリベラル主義。
押尾さんと二谷は保守主義。
芦川さんは勝ち、
押尾さんは負けた。
二谷は、芦川さんに負けることで、結婚や夫婦としては、勝っているわけです。負けるが勝ち。さすがに、高瀬さんは立命館大学の哲学科卒業だけあって、哲学がしっかりしている小説です。(ちなみに、一般社会で、哲学に関心を持つ女性は、とても少ないです。たいていは、文学へ行きます。)そして、背景には、勝ち負けを人為的に決めやすい、新自由主義の思想があります。つまり、一種の社会批判の哲学論文のような構成、構造をしている小説、と言えるわけです。
芦川さんは、仕事はできませんが、日本社会に支配的な、女性の専業主婦的な側面への期待を担う強さがあり、結果、仕事ができないにもかかわらず、職場の男性共同体からも守られ、ちゃっかり、二谷というエリートサラリーマンの妻の座も確保し、利他的に振る舞いながらも、全て勝っていきます。自分のしたいこと、できることが明確で、社会が、一見したところ、職場の論理で、労働力としての優秀さを求めているように見せながらも、その実、専業主婦、良妻賢母としての古典的なジェンダー役割を期待していることを敏感に嗅ぎ取り、そういった、男性共同体の期待する、本音の期待像を演じ、それによって、共同体の中で、勝ち組になっていきます。良妻賢母を演じる部分は、ある意味保守的な面も、大きいでしょう。しかし、利他性を演じながらも、その実、極端な利己主義である点は、リベラル思想と親和性が高い、と言えるでしょう。
押尾さんは、彼女もまた、ある意味、学校共同体の、女性への性的な役割期待としての、「チアガール」という役割を演じますし、職場では、ビジネスの有能なキャリア・ウーマンを演じますが、本心ではそれを嫌っています。おのれ自身としては、社会的な役割願望を演じることを嫌悪していますが、しかし、だからといって、自分にはこれといって、やりたいことがあるわけではない。つまり、利己性、エゴがそもそもやや弱く、本音では、女性への良妻賢母期待、チアガール的性的期待、職場のキャリアウーマン的期待の全てを嫌っているわけですが、いわば「消極的受容」で、他にやりたいこともなく、やるべきこともない。
それでも、社会の中で生きていかなければならないので、社会が期待する像を、表面的にはなぞりますが、それは仮面にすぎないので、その仮面性、虚偽性は、共同体を支える男性社会からは、危険人物とみなされ、良妻賢母の本音の男性期待と、共同体維持の必死さから考えて、男性と女性のジェンダー期待を分けて、それぞれの棲み分けを狙っている男性社会からは、押尾さんの中にある、本能的なジェンダー平等、男性と対等な女性の地位や権利を求め、狙う意識は、とても先鋭に映り、共同体維持を掲げる男性社会にとっては、危険人物に映ります。押尾さんは、とても敏感な、ジェンダー平等意識を、隠し持っています。
押尾さんにとって、過度に男性共同体社会の期待する女性像、良妻賢母を演じる姿勢は、いわば、強者である男性共同体社会に媚びを売り、結果、自己のエゴを通していく、とてもずうずうしいものに、映っています。「チアガール」という、男性の期待する、女性の性的シンボルを、いやいやながらでも演じた押尾さんのほうが、ずっと、男性のエゴに引き摺られて、男性の欲望を実現させる役割期待を演じなければ、女性の社会的な居場所がないという、先進国最低レベルのジェンダー平等意識しかない日本の現状に、憤り、いらだっています。「押尾さんは負けた」と語り手は語っていますが、実際は、語り手は、押尾さんのジェンダー平等意識に、深く共感し、コミットしています。「芦川さんは勝った」と語り手は語っていますが、実は、芦川さんはうわべだけ勝っただけ。本当に勝ったのは、芦川さんを背景で支える、男性的共同体社会で、そのさらに背景には、働く夫、家事育児を行い、良妻賢母を演じる妻、学び、遊ぶ子どもたち、そういった、「ふつうの」保守的な共同体社会の風景が、広がっているわけです。芦川さんは、その論理の上澄みに、ただ乗っているだけなのです。芦川さんを憎々しげに描く語り手は、芦川さんの勝利と、その背景にある、男性社会、さらにその後ろにある、働く夫と家事育児の妻と、学び遊ぶ子ども、という、その共同体の社会の論理を、否定し、嘲り、あげつらっているわけです。
二谷という若い男性サラリーマンが主人公なのも、示唆的です。つまり、若い男性サラリーマンの期待する妻、そして未来の家庭、良妻賢母の妻と、遊び学ぶ子ども、そして、たびたび、夜の女性だったり、働く女性だったりする、「共同体の外部の」女性、という、日本社会の女性への期待の保守的な側面を、示唆しているわけです。二谷は、芦川さんに、負けて勝つわけです。その背景には、将来の二谷が、中年やシニアの幹部層になった時、期待している、その女性像を、先取りしているわけです。
そして、芥川賞の女性作家も、男性社会の象徴たる、文藝春秋という社会の、無意識の願望に寄り添って、その地位を手に入れているわけです。
現代日本社会の、無意識の、あるいは意識の上の、男女の、ジェンダー相克に関心のある人に、おすすめです。(終)
参考文献
高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』 初版 二〇二二年 講談社








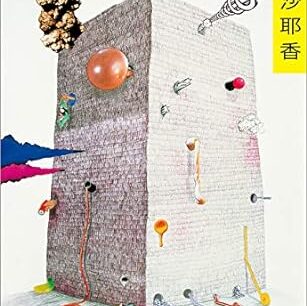

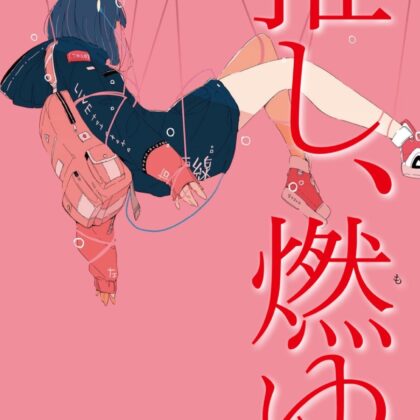


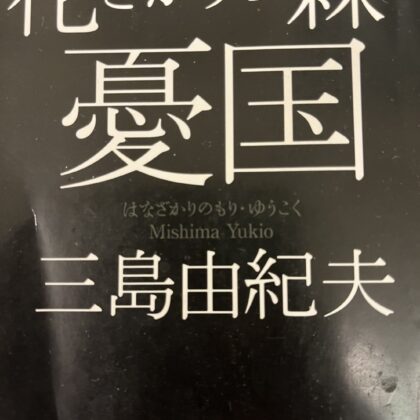


コメント